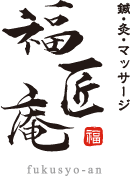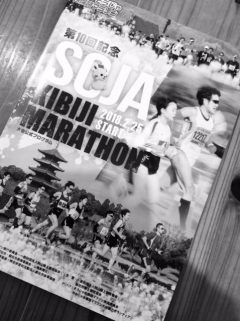変化を与える環境に
治療室
新年度、弊院は14年目を迎えます。
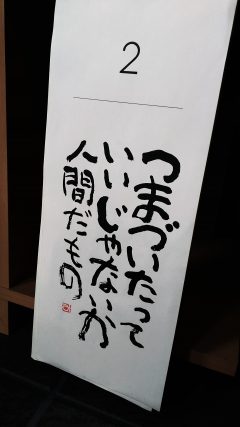
正月よりも4月1日開院のためか気持ち新たになるのはこの時季です。
前の年を省みて自分で次の1年のテーマを掲げますが
考えたことを現実にするのは、やはり日々の小さな能動的変化だと感じます。
経験や知識(情報)はこれの積み重ねでしかなく
より良い結果は、いかにそれに意識を集中させることができるかに懸かると思います。
よって、気持ち新たな時季とはいえ普段と何らやるべきことは変わりません。
しかし、子どもの進級や新生活を迎える人たちのニュースを耳にすると
ワクワクするし襟を正そうという気持ちになり
自分を取り巻く環境によって自分の気持ちや意識が変わることに気付きます。
心身に不具合を抱えて来院する方々に
弊院が変化を与えられる環境(存在)であるよう新年度も日々精進します。